

新科研基盤Cプロジェクト「デジタル遺産の適切な管理と運用に関する学際的国際比較研究」の主任研究者です。
This page is also available in English
東京の明治大学ビジネス情報倫理研の副所長を務めています。明治大学経営学大学院でも嘱託講師として教えています。メールアドレスはMeijiのaaaです(ac.jpドメイン名を使用しています)。
オフィスは明治大学駿河台キャンパスグローバルフロント棟408Gです。
次の専門団体の会員です。
ACM: 現在、出版委員会直属の倫理および盗作委員会の委員です。前に SIGCAS, の執行委員の委員でした。2011年から2014年にかけた委員長でした。2014年から2017年にかけた前委員長でした。
Asian Privacy Scholars Network のメンバーでもあり、そ の運営委員会のメン バーとして選ばれました。
オープン フォーラム アカデミーのフェローです。
LinkedIn、 Community of Science と Academia.eduにプロフィールがあります。
リーズ大学で数学と計算科学の学士号、同じくリーズ大学でコンピュータの修士号、セント アンドリュース大学でコンピュータ サイエンスの博士号、レディング大学出身でおよび高度な法学のLLM(法学修士号)を取得しています。
こちらは私の仕事のページです。私はブログだけでなく、個人的なページ (趣味や興味に関するリンク、そのようなもの) もあります。
コンピューターと通信テクノロジーの社会的、法的、倫理的側面を研究している学際的な研究者です。
以前、計算論理とコンピュータ数学の研究に従事していました。詳細については、以下を参照してください。
ここでは、現在の研究プロジェクトの詳細と、特に支援されている資金の詳細を示します。完了したプロジェクトの詳細については、以下を参照してください。
プライバシー、および監視とセキュリティに関連する問題は、私の中心的な関心と専門分野の一つです。
2007 年から日本政府の ID システムを研究しています。その一環として、2012 年 9 月から 12 月にかけて、UNSWのGraham Greenleaf教授によるJSPS 客員フェローシップ(L12535)を主催しました。日本の新しいマイナンバー システムに関する記事については、出版物リストを参照してください。 。これに関する初期の研究をNet-ID 2009カンファレンスで発表し、最近では 第 3 回アジアプライバシー学者ネットワーク学会で 「日本政府国民登録制度の注釈付きタイムライン」について講演しました。
レディング大学のシャーリー・ウィ リアムズ教授およびナズ・ラソール教授とともに、 スリランカの情報通信技術 と遠隔教育:2つの大学のケーススタディに関す るタ リンドゥ・リヤナグナワルデナ博士の博士号を指導しました他にも多数掲。 載しております書類も一緒に。
引き続き、相互作用の問題に興味を持ち、研究し続けています。コンピュータ および通信技術(遠隔学習やAIと教育。
2010年、KDDI研究財団はビジネス情報倫理研に資金を提供し、「日本と英国の若者のオンライン行動に関する比較研究」を実施した。このプロジェクトの主な成果物は、デジタル アイデンティティの管理に関する学生向けのトレーニング資料に関するレディング大学システム工学部のシャーリー ウィリアムズ教授とそのチームの成果の言語的で文化的に翻訳でした。ビジネス情報倫理研は、大学生向けにオリジナルの教材を日本語に翻訳することに加えて、日本の中学生と高校生向けのバージョンも作成しました。
Asian Privacy Scholars 第 4 回簡単なプライバシーに関する国際会議は、2014 年 7 月に東京の明治大学で開催されました。
会員と会議組織を監督する APSN事務局のメンバーとして選ばれました。
Asian Privacy Scholars のソーシャル ネットワーク世界におけるプライバシーに関する第 2 回国際会議が、2012 年 11 月に東京の明治大学で開催されました。
USEC 13: 2013年使えるセキュリティに関するワークショップは、 金融暗号とデータセキュリティ2013カンファレンスのワークショップとして、2013年4月に沖縄で開催されました。
以下の進行中の一連のカンファレンス/ワークショップに定期的に参加しています。
ここでは、以前の研究プロジェクトの詳細と、特に支援されている資金の詳細を示します。現在のプロジェクトの詳細については上記を参照してください。2010 年 4 月に英国から日本に移住したということは、これらのプロジェクトの一部は私が去った後に他の人によって完了されたことを意味します。
明治大学のEU Horizon 2020 RRING プロジェクトの共同研究者および研究員でした。
このプロジェクトでは、EU の RRI (責任ある研究とイノベーション) 概念に対する世界中の同等の国際的なアプローチを調査しました。研究に資金を提供し、研究とイノベーションを実施し、研究の最終結果を展開する組織を含む、RRI に関与する組織の国際ネットワークを構築しました。
JSPS助成金Easy Security and Privacy (科研費 (B) 15H03385) (2015-2018)の研究代表者を務めました。
日本学術振興会「ICTを活用したサービスと組織の社会的責任に起因する疎外に関する異文化分析」(科研費(B)25285124、研究代表者:村田圭一教授)の共同研究者(2013年~2016年)を務めました。
CBIEは、2014年から2018年まで、ユーザー管理の個人情報利用システムのユーザー受容性調査を支援する契約をKDDI総合研究所と結んでいた。私たちは、ATR および ATR の研究者と無償で協力し続けています。
文部科学省の私立大学戦略的研究拠点整備事業(2012-16年度)「組織の情報倫理」(S1291006)の共同研究員の一人でした。
日本学術振興会の助成金「ソーシャルメディア時代の組織と個人の行動と個人情報保護」(科研費 (B) 24330127)の研究代表者として、プライバシーの問題に影響を与える法律、ビジネス、技術、社会のルールを調査しました。
英国のEPSRCは、2008 年から 2010 年にかけて、「日英情報倫理: 比較と相互受精」(EP/G069808/1) の助成金により、村田教授および折戸博士と共同研究する明治大学への訪問を支援しました。
王立工学アカデミーは、世界研究賞を通じて 2007 年のサバティカルな東京訪問を支援しました。この間、私は明治大学の客員教授も務めていました。
EPSRC プロジェクトの理由(EP/C533402)
フェリーマン博士、ウェイ博士、そして私は、 レディング大学 この英国のEPSRC プロジェクトは、UCL とキングストンの学者とともに 大学は、社会的、法的、倫理的な影響を検討しています。 ビデオ分析アプリケーション。
EU Framework7セキュリティテーマプロジェクトSUBITO (FP7-218004)
パートナーには、SELEX S&AS (Finnmeccanica の一部)、フランス原子力委員会、リーズ大学が含まれます。
EU フレームワーク7セキュリティテーマプロジェクトEFFISEC (FP7-217991)
パートナーには、SAGEM防衛安全保障部門、タレス、スウェーデン国防研究庁、ルーマニア国境警察、リスボン港が含まれます。
EU フレームワーク7セキュリティテーマプロジェクト IMSK (FP7-218038)
パートナーには、Saab AB、Telespazio、フランス内務省、ドイツフットボール リーグが含まれます。
EU PASR プロジェクトBIO3R (2007-9)
パートナーには、Universitaetsklinikum Bonn と Nomisma S.p.A.が含まれます。
EU PASR プロジェクトEuropCop (2007-8)
EU PASR プロジェクトISCAPS (2005-7)
明治大学のEU Horizon 2020 EU-Japan.AI プロジェクトの共同研究者および研究員でした。
このプロジェクトは、製造業向け AI の研究、革新、展開に取り組むヨーロッパと日本を拠点とするさまざまな関係者グループ間の連携を確立し、強化することを目的としていました。
フランスの CIGREF 財団 は、ISD研究プログラムの一環として、東南アジアにおけるデジタルオブジェクトの使用に関する新たな倫理的価値観を調査するためにCBIE に資金を提供しました。
イアン ブラウン博士 (当時 オックスフォード インターネット研究所) と、著作権問題とユビキタスコンピューティングによって引き起こされる倫理的問題について 医療システムでをコラボしました。
私は(レディング大学のレイチェル・マクリンドル博士と)情報社会の社会的および専門的問題に関する教科書を共著しました。2007年12月にWileyから出版された『パンドラの箱』。
2004年11月にレディング大学で "Copyright v Creativity"についての公開講義を行いました。
仕事の中で可能な限り一般の人々のデジタル権利を推進しており、これに対するさまざまなアプローチに少しずつ関わっています。
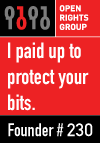
Open Rights Group (ORG)
の創立1000人の1人にいます。
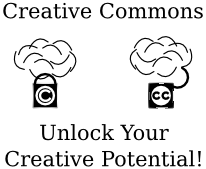
クリエイティブコモンズの概念を支持しており、この画像などの私の作品の一部をCCライセンスに基づいてリリースしています。
前に非営利ユーザーの選挙区(NCUC) (ICANNの一部)の個人会員でした。
以前はコンピューター数学の研究をしていましたが、現在は社会的、法的、倫理的な影響に焦点を移しています。
TransNumbersの正式なプレゼンテーションについてアンダーソン博士のパースペックス関連計算のマシンモデルについて、 ジェームス アンダーソン博士 (レディング大学、現在 退職)そして ノーバート フェルカー博士 (エセックス大学) と一緒に働きました。
高次の定理の証明:
The Coq Systemで
博士号PhDの研究をしました。
PVSも使いました。
定理証明者の機能とコンピューター代数システムを組み合わせるCalculemus Initiativeに参加しました。
2001年にSaarlandes大学でSiekmann教授のグループとの共同研究しました。
数学的知識管理:
数学的知識管理の新しい分野の初期調査を行ったEU 5th Frameworkプロジェクト
MKMNet
のメンバーでした。会議の審査員の一人が「MKMのマニフェスト」と呼んだこの作業の一般的な方向性に関する私の見解については、MKM'03学会での私の論文:Digitisation, Representation and Formalisation。
2006年のMKM カンファレンス の会議議長を務めました。
出版物 (2024年5月13日時点の最新のものです)。.
大学院学位の論文はすべて入手可能です。
INDUCT: A Logical Framework for
Induction Over Natural Numbers and Lists Built in SEQUEL
(リーズ大学コンピュータサイエンスの修士論文、1995年)
Tools and Techniques for Machine-Assisted Meta-theory
(セントアンドリュース大学、コンピューターサイエンスの博士論文、1997年)
The Road to the EUCD
(LLM法学論文、レディング大学、2005年)
残念ながら、明治大学での私の現在の立場では、研究生を指導することはできません。 CBIEには可能性があるかもしれません。
学部生のインターンには全く興味がありません。インターンシップを探しているインド工科大学 (または類似の)学生からのメールは無視されます。.
これまで、情報社会(明治大学のさまざまな大学院生を対象)から、離散数学、プログラミング設計手法、関数型プログラミングなどの技術科目(レディング大学のコンピューティングおよびその他のシステム工学の学生を対象)まで、幅広いクラスを教えてきました。
メールアドレスは明治のaaa (ac.jpドメイン名を使用しています)